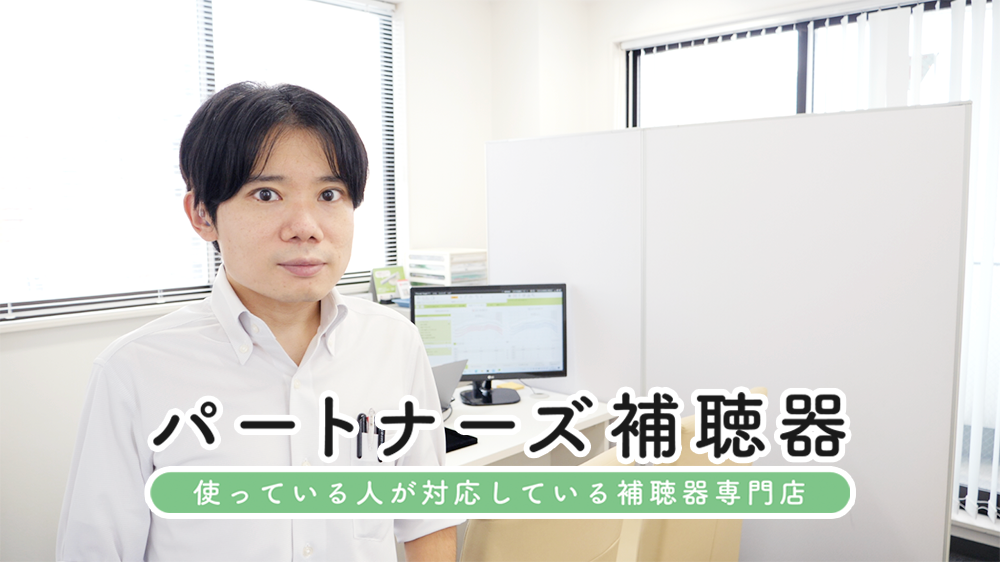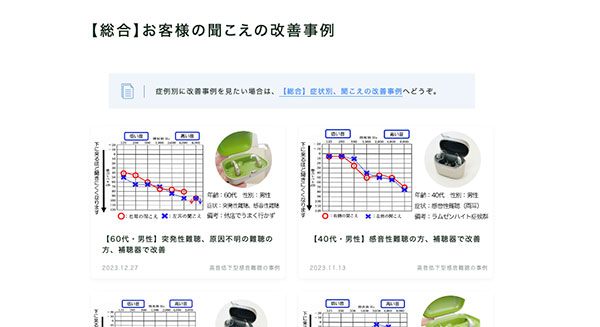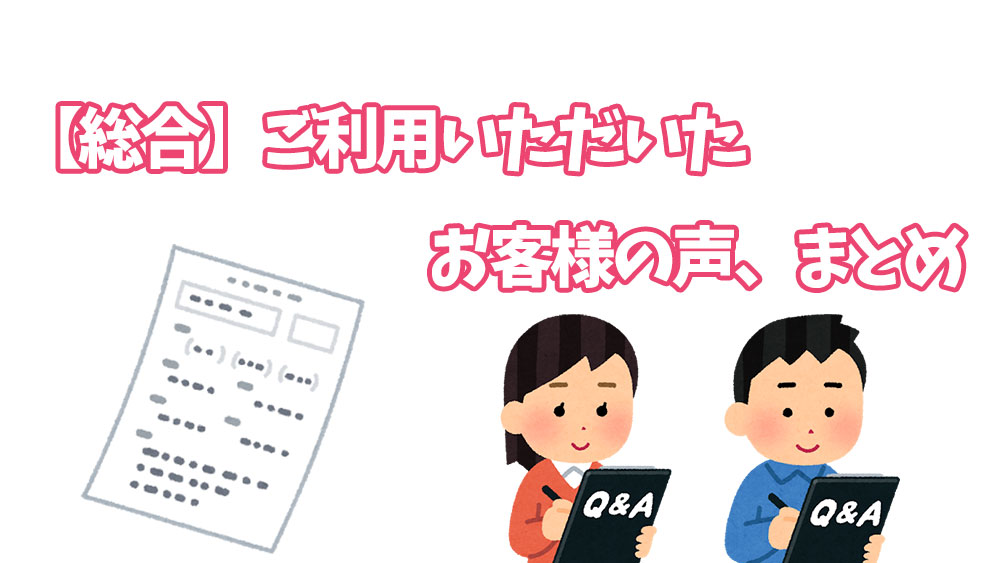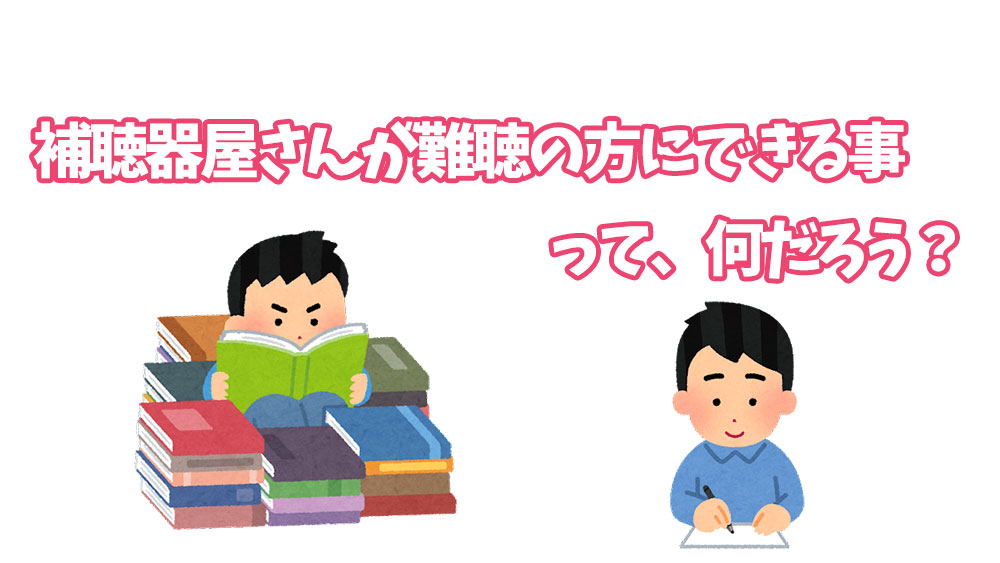他の業界の人とお話して感じた補聴器のハードルの高さ

少し前に他の業界の方、業種の方とお話する機会があったのですが、そこで改めて感じたのは、補聴器のハードルの高さでした。
補聴器の場合、少しずつ耳に補聴器をなれさせたり、聞こえを改善していく必要があるため、何度か通っていただく必要があります。
ご高齢の方の場合は、ご家族の方も連れ添っていただく事が多く、ご家族共に負担がかかりやすい状態になりがちです。
私のお店は、少し特殊なので、あまり気にしていなかったのですが、確かに言われてみれば、そうだよね。と、改めて感じる機会がありましたので、その事に関して、書いてみます。
補聴器を必要とする人
今現在、補聴器を必要とする人、もしくは、聞きにくさを感じている人は、圧倒的にご高齢の方が多いです。
若い方や生まれつき難聴の方もいますが、生まれつきの難聴の方は、1000〜1500人に一人くらいの確率で、0.1%未満です。
さらに、聞こえる状態で生まれたとしても、もちろん、病気になってしまい、聞きにくくなる方もいます。しかし、そのような方でも、多い難聴で、これもまた、1000人に1人くらいです。
しかし、年を重ね、加齢によって難聴になる方は、かなりの確率です(中には、年を重ねても難聴にならない人もいます)。
補聴器を必要とする、もしくは、聞こえにくさを感じる方は、高齢者が90%以上で、若い方(ここでは、50代未満)は、かなり少ないのが現状です。
高齢の方の主な補聴器パターン
ご高齢の方の場合、ご自身から自覚するケースももちろんありますが、多いのは、ご家族からの指摘です。
- テレビの音が大きい
- 呼んだのに、返事をしない
- 言った事が伝わっていない
これらの事で、ご本人というよりも、家族の方が困ってしまい、聞きにくさを改善しようとするケースが、圧倒的に多いです。
耳が聞こえにくくなったとしても、人と会話しない限りは、困りにくいため、自分自身で自覚する事が難しくなります。
これが、会社で働いていたり、ボランティアによく参加する。という方であれば、その場所で、困る事が増え、ご自身が自覚することはあります。
しかし、ご自宅の中によくいるケースなどでは、自覚しにくい傾向があります。
補聴器を使うまでに登らなければならないハードル
補聴器を使うようになるためには、
- 補聴器を自分から使い、慣れる必要がある
- 何度か、病院さん、補聴器屋さんに通う
の2つが必要です。
基本的に耳の状態に合わせ、少しずつ、聞きにくさを改善していくのが補聴器です。そのため、少しずつ、改善させていきます。
また、聞きにくくなった耳の状態に慣れていると、急に聞こえるようになる事で、わずらわしく感じる事もあります。
そして、自分が補聴器をつけている人間だからこそ感じますが【自分の感覚が変わる】というのは、基本的に、あまり良い感覚はしません。
慣れてくると、そのような感覚すらなくなるのですが、どうしても初めは、異質に感じやすいです。
それらのこともあり、少しずつ改善していく事が多くなります。
他の方と話して感じたハードルの高さ
前置きが長くなってしまって申し訳ないのですが、こちらの方とお話して、感じたのは、補聴器を使うハードルの高さでした。
何度か通う必要もあるというところもそうですが、実際に自分の耳の状態が変わるようになるため、ご本人も補聴器を使い続けていく必要があります。
ご自身から変わる。もしくは、聞こえるようになりたい。という欲がある方は、うまく行きやすいのですが、それがない方。つまり、ご家族に言われ、嫌々連れて来られる方には、ハードルがかなり高くなります。
また、仮にご自身から使う意欲がある方でも、何度も通うと、疲れやすく、毎週通うとなると、結構、疲れる事も多いです。
こちらの方も、実は、ご両親が聞きにくくなり、ご家族の一人として、付き添いで、補聴器屋さんにご両親と行っているようですが、「2回目ですが、すでに心が折れそうになっています。」という風に言っていました。
これは、補聴器を使いこなすためには、それだけの時間が必要な事。そして、基本、付き添いで行っているため、ご自身も含め、ご家族にも負担がかかりやすくなってしまう事、この2点によってです。
ハードルの高さも普及しづらい要因になっているのかもしれない
私自身が感じたのは、このハードルの高さも普及しづらい要因になっているのかもしれない。と、いう事です。
自分の家族に負担がかかるものや、何度も通う必要があるとなると、それなりの負担がかかります。
自分と異なる業種の方とお話していて、切に感じたのは、この部分でした。どうしても、業界が長くなると、それが当たり前のように感じてしまい、さらには、丁寧に対応する事が、良いことのように錯覚する事すらあります。
もちろんそれも一つの解ではあるのですが、人によって、結構、変えていかなければならないな。というのを、このお話で、感じました。
自分なりに、このハードルをどう下げられるのか。それが、普及するための課題となりそうです。