当店の取り扱い補聴器

深井 順一|パートナーズ補聴器
こちらでは、主に当店で扱っている補聴器や製品について記載していきます。
補聴器の形、種類には、いくつかありますが、主に扱っている製品に関しては、以下の通りです。ご参考にどうぞ。
- メーカーWebサイト:フォナックジャパン
- 総合カタログ:フォナック総合カタログ(PDF)
Contents
補聴器(フォナック)
耳かけ形補聴器
RIC補聴器(リック補聴器)
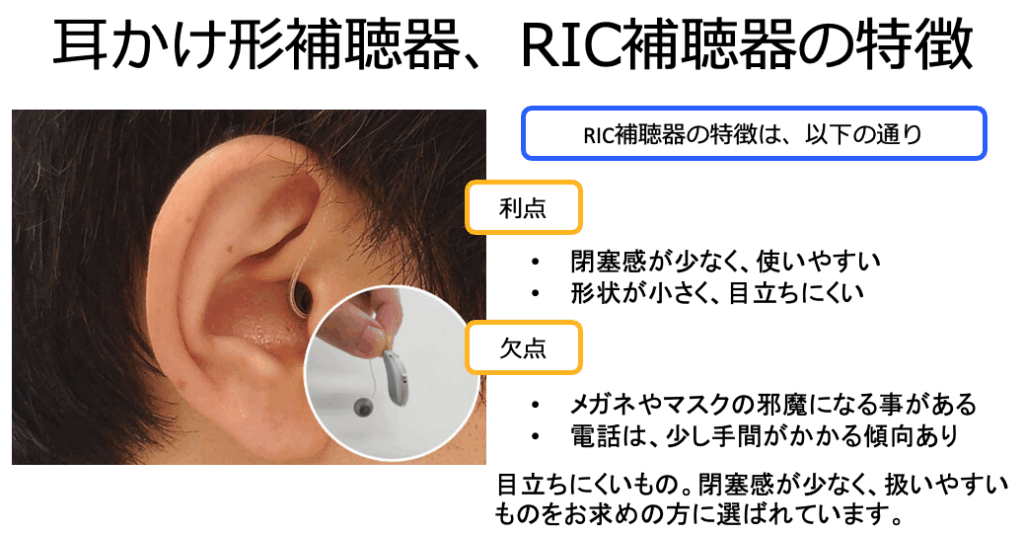
充電タイプのRIC補聴器

- 充電時間:約3時間でMax
- 使用時間:〜20時間(フル充電)(連続使用時間)
- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能
ボタン電池形タイプのRIC補聴器

- 電池:空気電池式(ボタン電池)
- 使用時間:60〜85時間(電池一つで、5〜7日)
- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能
標準BTE補聴器(標準ビーティーイー補聴器)
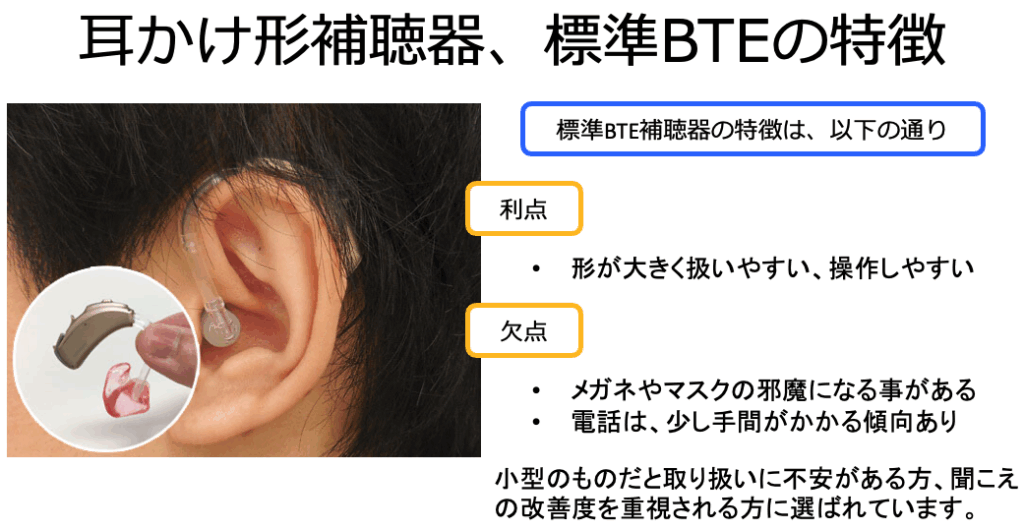
充電タイプのBTE補聴器

- 充電時間:約3時間でMax
- 使用時間:〜18時間(フル充電)(連続使用時間)
- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能
ボタン電池タイプのBTE補聴器

- 電池:空気電池式(ボタン電池)
- 使用時間:65〜100時間(電池一つで、6〜9日)
- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能
耳あな形補聴器
補足トピック
CIC補聴器(シーアイシー補聴器)
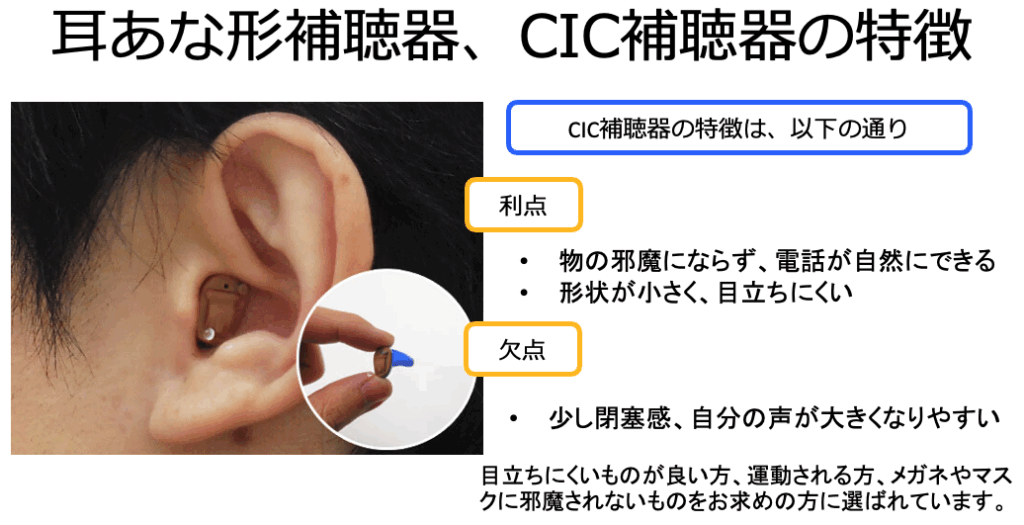

- 電池:空気電池式(ボタン電池)
- 使用時間:55〜75時間(電池一つで、4〜5日)
ITC補聴器(アイティーシー補聴器)
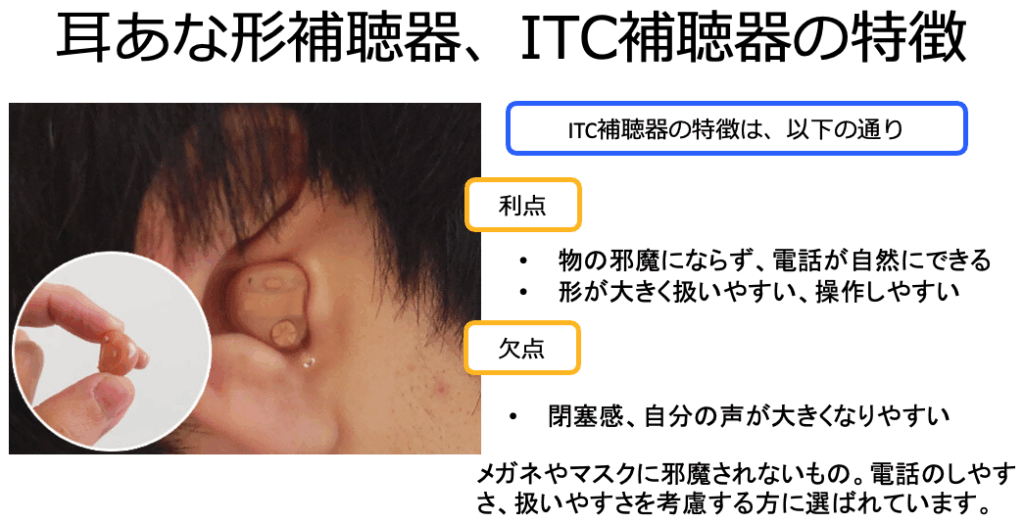

- 充電時間:約3時間でMax
- 使用時間:〜30時間(フル充電)(連続使用時間)
- 備考:Bluetooth接続可能、アプリで調整可能
クロス、バイクロス補聴器(フォナック)
バイクロス補聴器
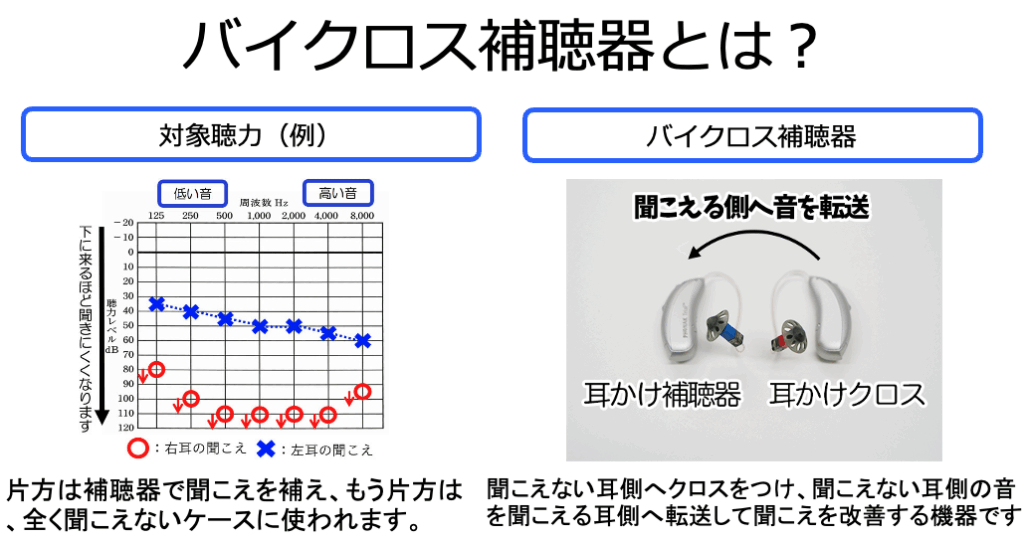

- 充電時間:約3時間でMax
- 使用時間:〜16時間(フル充電)(連続使用時間)
- 備考:クロスと補聴器、セットでないと使用不可
- 詳細:バイクロス補聴器って、どんな補聴器?
クロス補聴器
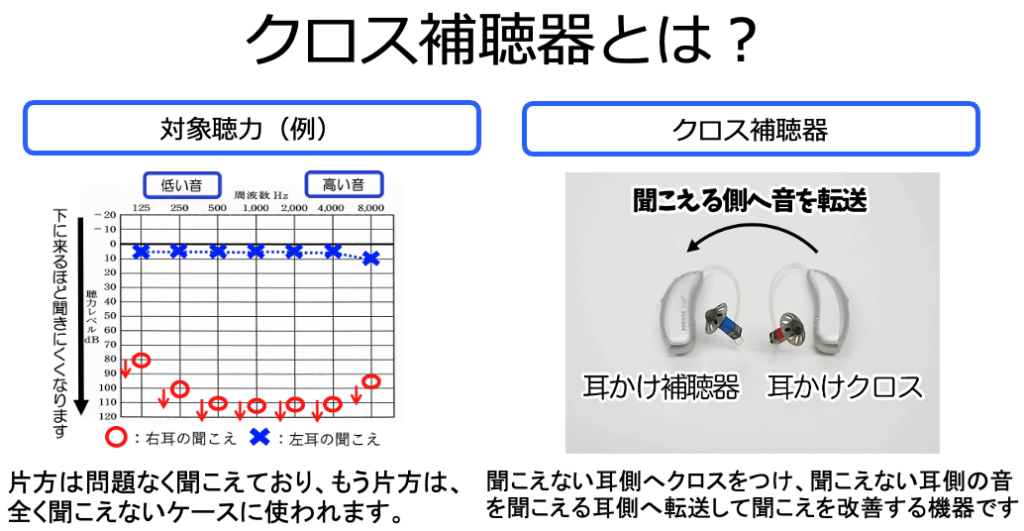

- 充電時間:約3時間でMax
- 使用時間:〜16時間(フル充電)(連続使用時間)
- 備考:クロスと補聴器、セットでないと使用不可
- 詳細:クロス補聴器って、どんな補聴器?
サポート用品
イヤモールド

- 効果:耳から外れにくくしたり、より聞こえを改善するもの
- 使用:BTE型の補聴器に使用
- 価格:@11,000円
- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり
SPシェル

- 効果:耳から外れにくくしたり、より聞こえを改善するもの
- 使用:RIC型の補聴器に使用
- 価格:@11,200円〜23,100円
- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり
クロスチップ

- 効果:耳から外れにくくするもの
- 使用:クロス型の機器に使用
- 価格:9,823円
- 備考:3ヶ月間無償の作り直し期間あり
補聴援助システム(ロジャー)※フォナック
補聴援助システムとは?
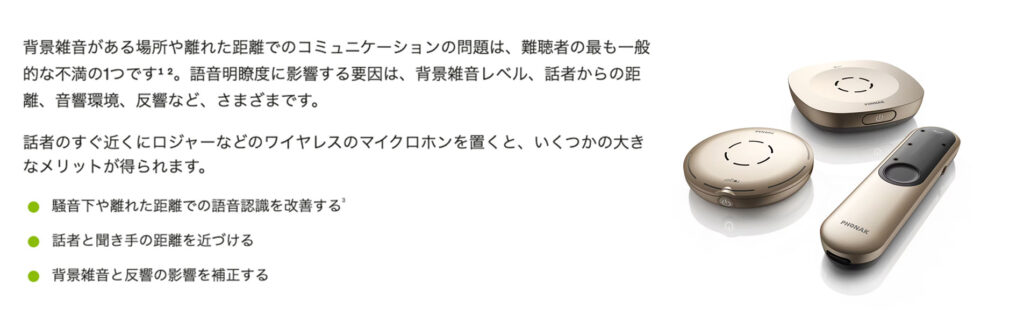
- 概要:補聴援助システム
- 特徴:補聴器では改善しづらい離れたところ、騒がしい環境をより改善する機器
- 備考:補聴援助システム、ロジャーとは?
送信機
ロジャーセレクト(送信機)

- 金額:209,000円(税込)
- タイプ:成人用、送信機
- 使用可能飛距離:25m以内
- 充電:約2時間
- 使用時間:8時間(フル充電、連続使用時間)
ロジャーオン(送信機)

- 金額:209,000円(税込)
- タイプ:成人用、送信機
- 使用可能飛距離:25m以内
- 充電:約3時間
- 使用時間:8時間(フル充電、連続使用時間)
ロジャーテーブルマイク(送信機)

- 金額:209,000円(税込)
- タイプ:成人用、送信機
- 使用可能飛距離:25m以内
- 充電:約4時間
- 使用時間:16時間(フル充電、連続使用時間)
受信機
汎用形受信機

- 金額:@44,000(税込)
- タイプ:補聴器に直接つけるタイプ
- 備考:汎用型の場合、別途オーディオシューが必要
ロジャーネックループ
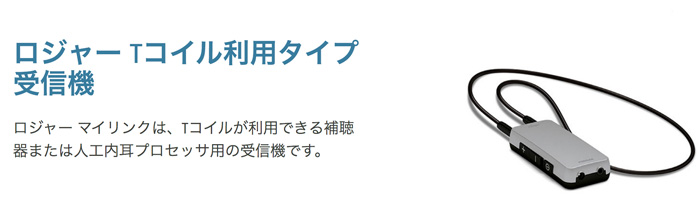
- 金額:@44,500(税込)
- タイプ:首にかけて使うタイプ
- 備考:使用には、補聴器側にTコイル設定が必要
